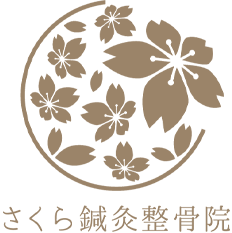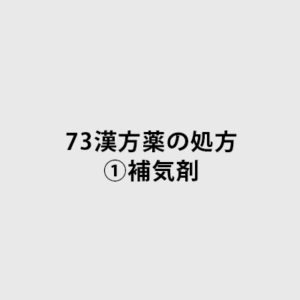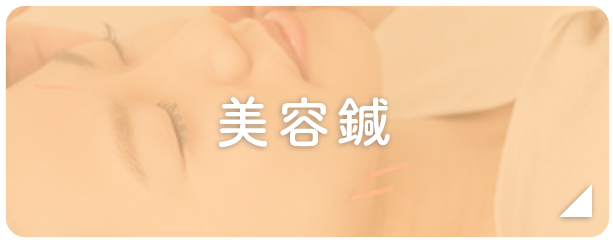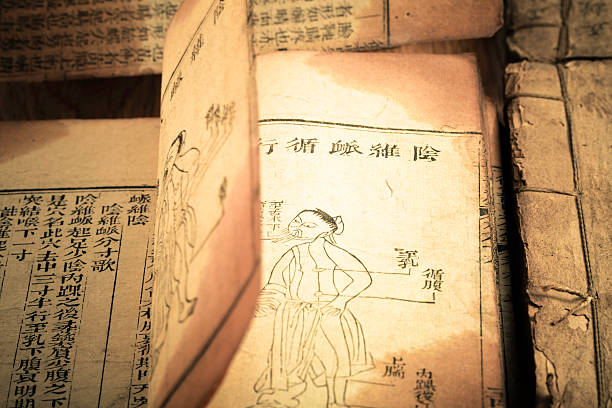第一章 東洋医学の基礎知識
アジアで生まれた伝統医学
東洋医学の統一体観
なぜ病気になるのか
気・血・津液・精
気の外燃
気が不足すると病気になる
血と津液について
精と神
気・血・津液の変調① 気の変調
気・血・津液の変調② 血の変調
気・血・津液の変調③ 津液の変調
精の不足
五臓六腑とは何か
五臓一心・肺・脾・肝・腎
六臓一胆・胃・大腸・小腸・膀胱・三焦
五行説と五臓六腑
五臓の変調① 心の変調
五臓の変調② 肺の変調
五臓の変調③ 脾の変調
五臓の変調④ 肝の変調
五臓の変調⑤ 腎の変調
六臓の変調
五臓の色体表
五臓関連図
3種類の病因
病因① 外因
病因② 内因
病因③ 不内外因
column アメリカの鍼灸事情
第二章 診療法と証
四診と弁証論治
八綱弁証で証を決める
望診 まずは目で観察
舌診 舌を見てわかること
聞診 聞くこと、においをかぐこと
問診① 汗と熱
問診② 痛み
問診③ 飲食、睡眠、排泄
問診④ 問診票で五臓をチェック
切診① 脈をみる脈診
切診② 腹部に触れる腹診
虚証と実証
虚証6種類
実証6種類
治療方法は法則にしたがう
実際の弁証例① せきがでる
実際の弁証例② 耳鳴り
実際の弁証例③ 不眠とめまい
column イギリスの鍼灸事情
第三章 経絡とツボ
気と血の通り道、経路
おもな経路
正経十二経脈
経絡とツボの関係は?
鍼灸治療とは
WHO認定の鍼灸適応症
治療によく使われるツボ
ツボの名前と奇穴
耳ツボ療法
鍼治療① 治療に使う鍼の種類
鍼治療② 鍼の手技
鍼治療③ 鍼と漢方薬
灸治療① もぐさがゆっくり燃える灸
灸治療② 灸の効果
手技療法① マッサージ
手技療法② 按摩と指圧
吸玉療法
column ヨーロッパ諸国の鍼灸事情
第四章漢方薬と薬膳
漢方薬は東洋医学の治療薬
証と漢方薬
漢方薬が効果的な症状と病気
服用期間と副作用
漢方薬の処方① 補気剤
漢方薬の処方② 補血剤
漢方薬の処方③ 補陰剤
漢方薬の処方④ 補腸剤
漢方薬を試してみようと思ったら
薬食同源(医食同源)① 五性と五味
薬食同源(医食同源)② 薬膳
column アーユルヴェーダなどの伝統医学
第五章 日本における東洋学の可能性と将来
気功と太極拳
緩和医療現場での鍼灸
透析治療の症状を鍼で緩和する
鍼治療による誤嚥性肺炎と転倒の予防
人間ドックと東洋医学
脳血管障害の後遺症を鍼治療で改善
鍼刺激の脳への作用研究最前線
医学部における鍼灸医療教育への取り組み
美容鍼灸
褥瘡と歯科での鍼治療
スポーツ鍼灸
鍼灸師になるためには
東洋医学の歴史① 中国伝統医学の原典
東洋医学の歴史② 中国の伝統名医たち
東洋医学の歴史③ 日本での東洋医学発展と衰退
東洋医学の歴史④ 日本と中国の現状